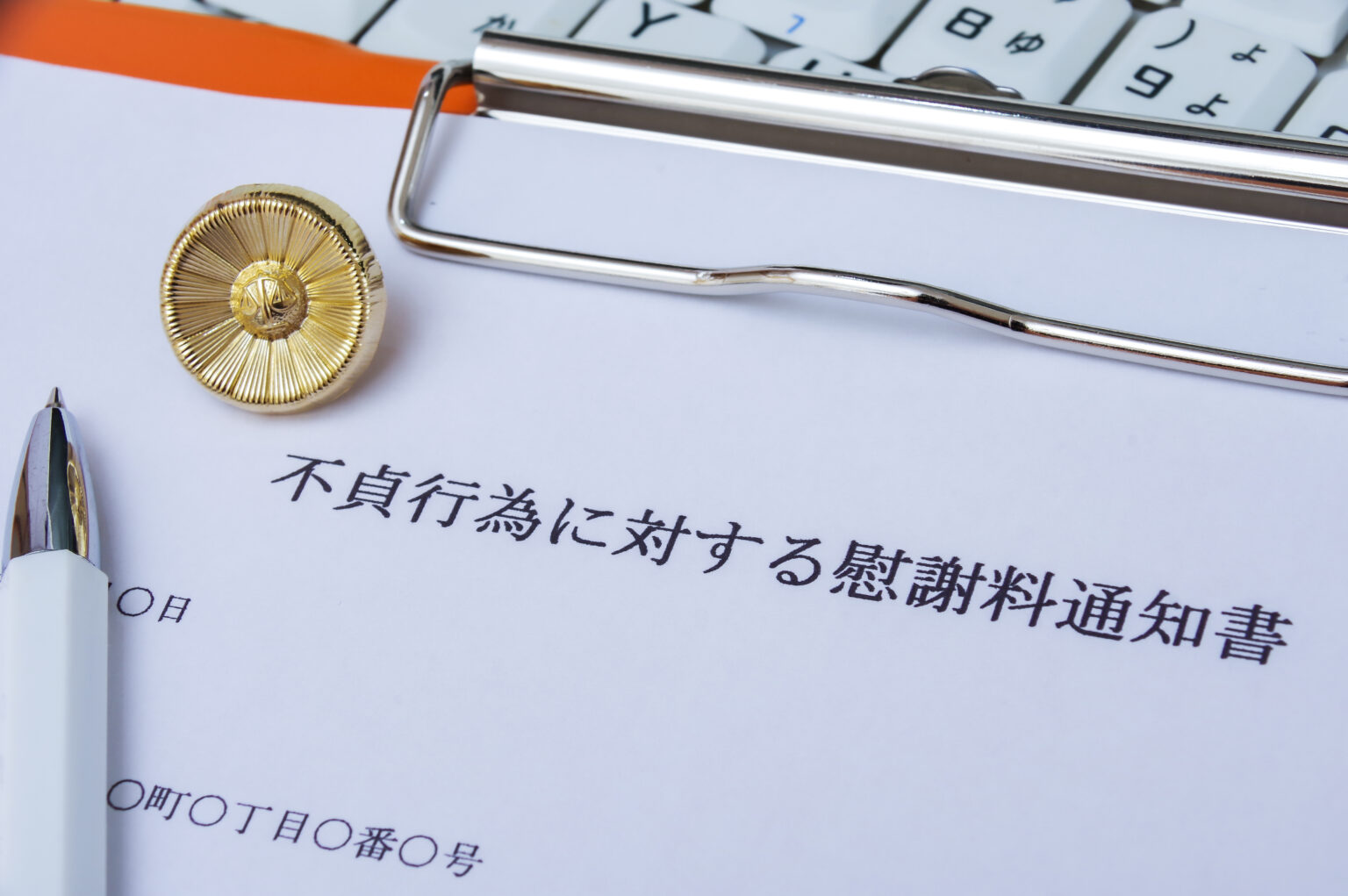信頼していたパートナーである妻に浮気をされたという事実は、計り知れないショックと悲しみをもたらします。裏切られたという感情から、今後どう対応すべきか、途方に暮れてしまう方も少なくないでしょう。
妻に対して償いを求めるには何が必要なのか、もし離婚を選ぶなら、どのような点に注意すれば良いのか、あるいは浮気の相手方にも責任を問えるのか。疑問や不安は尽きないはずです。
この記事では、妻の浮気が発覚した場合の慰謝料の目安、慰謝料を求める際の重要な点、そして離婚に進む場合の注意点などを、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
妻が浮気したら…法律上「慰謝料請求」が可能
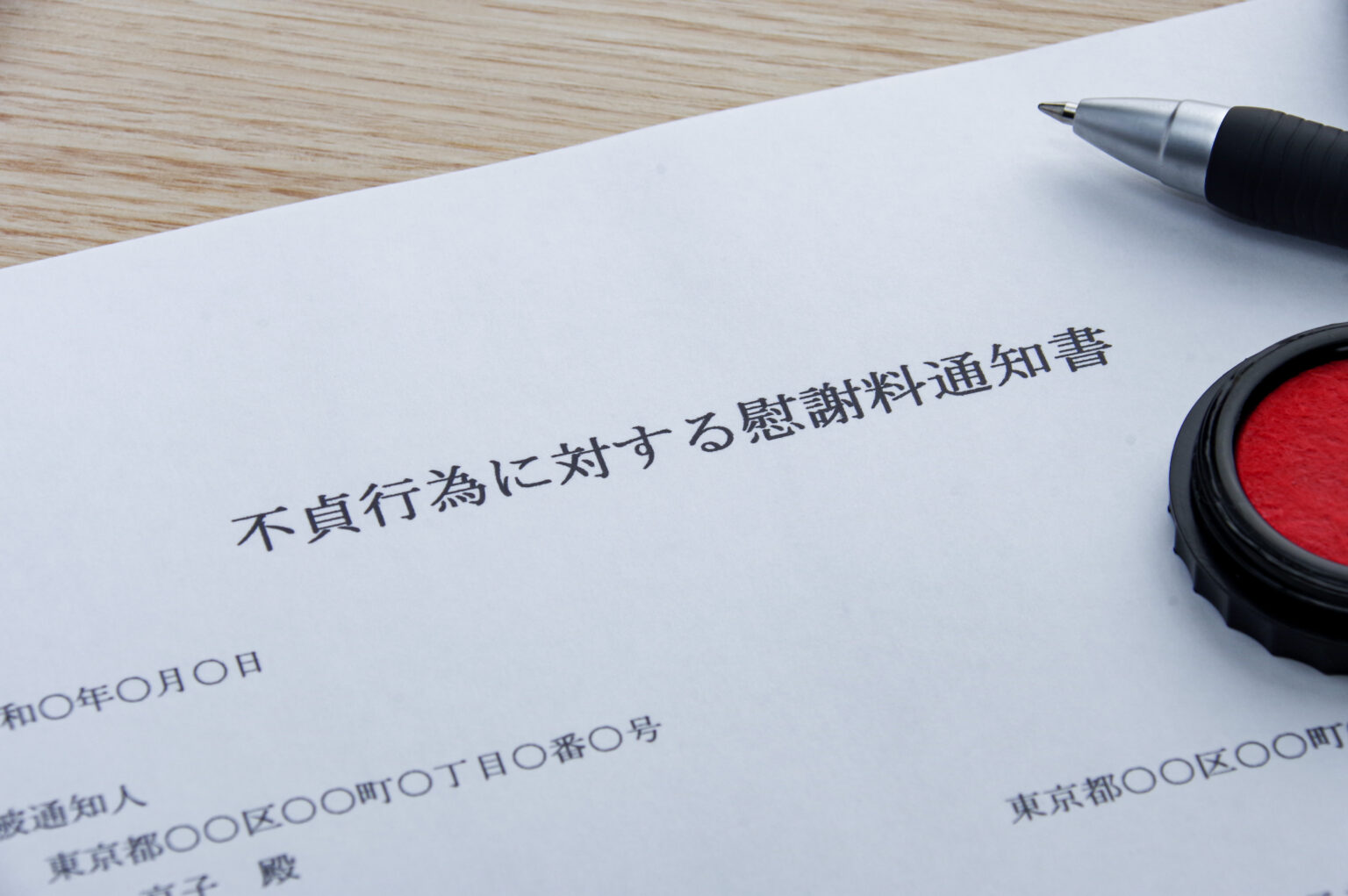
妻が浮気(法律上は「不貞行為」といいます)をした場合、原則として、夫は妻とその浮気相手の両方に対して、精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料を求めることができます。
ここでは、それぞれに対する慰謝料請求で押さえておくべき点を確認していきましょう。
妻へ慰謝料請求する場合のチェックポイント
妻が浮気をした事実があれば、離婚するかどうかにかかわらず、妻本人に対して慰謝料を請求する権利があります。その際に重要となるのは、以下の点です。
- 不貞行為(肉体関係)の事実があったこと
- 浮気以前から夫婦関係が壊れていなかったこと
- 夫側に浮気の原因となるような責任がないこと
- 慰謝料請求権の時効が過ぎていないこと
慰謝料を請求するためには、まず妻が浮気相手と肉体関係を持ったという「不貞行為」の証拠が不可欠です。
また、例えば5年以上の長期別居など、妻の浮気が始まる前から既に夫婦としての実態が失われていた(夫婦関係が破綻していた)と判断される場合、慰謝料請求は難しくなります。同様に、夫によるDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメントなどが原因で妻が浮気に至ったようなケースでは、婚姻関係を壊した責任の一端は夫にもあると見なされ、慰謝料請求が認められない、あるいは減額される可能性があります。
さらに、慰謝料請求権には時効があります。「不貞行為の事実」と「浮気相手が誰か」を知った時から3年が経過すると、時効によって請求する権利が消滅してしまいます。もし数年前の浮気について慰謝料請求を考えているなら、時効が成立していないかを事前に確認することが必須です。
加えて、注意点として、もし妻の浮気相手も既婚者であった場合、その相手の配偶者からあなたの妻に対して慰謝料請求がなされる可能性があります。そうなると、あなたが妻から慰謝料を受け取ったとしても、夫婦全体の家計としては差し引きゼロ、あるいはマイナスになってしまうケースも考えられることを念頭に置いておきましょう。
浮気相手へ慰謝料請求する場合のチェックポイント
妻の浮気では、その相手方に対しても慰謝料を請求することが可能です。浮気相手への請求では、妻への請求で挙げたポイントに加えて、以下の点が重要になります。
- 浮気相手に故意または過失があったこと
- 浮気相手が自由な意思で肉体関係を持ったこと
- 不貞行為によって「平穏な婚姻生活を送る権利」が侵害されたこと
- 妻から受け取る慰謝料と合わせて、本来認められる賠償額を超えないこと(二重取りは不可)
浮気相手に慰謝料を請求するには、相手が「妻が既婚者であること」を知っていた(故意)、または注意すれば知り得たはずなのに知らなかった(過失)という事実が必要です。 【故意の例】:妻から既婚者であると聞いていた。 【過失の例】:妻が日常的に結婚指輪をしていたのに、独身だと軽信した。
また、浮気相手が自らの意思で関係を持ったことも条件です。例えば、妻が「関係を持たないと、あなたの配偶者に浮気の事実を暴露する」などと脅迫して関係を強いた場合、浮気相手はむしろ被害者であると考えられるため、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。
慰謝料は、浮気によって「夫婦として平穏に暮らす権利」が侵害されたことに対する賠償です。この権利侵害は、妻と浮気相手の共同行為によって引き起こされた一つの損害と見なされます。そのため、損害全体に対して認められる賠償額(例えば200万円)を、妻と浮気相手からそれぞれ全額(合計400万円)受け取るような「二重取り」はできません。妻から一部(例えば100万円)を受け取った場合、浮気相手には残りの範囲(100万円)までしか請求できません。
妻の浮気における慰謝料の相場は?

慰謝料の相場観を把握しておくことは重要です。相場を知らないと、本来得られるはずの金額よりも低い額で合意してしまい、不利益を被る可能性があります。適正な金額を請求するためにも、事前に目安を理解しておきましょう。
慰謝料の一般的な相場
妻の浮気に対する慰謝料の一般的な目安は、50万円から300万円程度とされています。
ただし、これはあくまで目安です。実際の金額は、離婚に至ったかどうか、浮気の具体的な内容(期間、頻度、悪質性など)、証拠の有無、当事者の反省の度合いといった様々な事情を、個別のケースごとに総合的に考慮して決定されます。
以下に、状況別の慰謝料相場の目安を示します。
- 浮気が原因で別居に至った場合:100万円~150万円程度
- 浮気が原因で離婚に至った場合:100万円~300万円程度
- 浮気はあったが婚姻関係を続ける場合:50万円~100万円程度
浮気の事実がありながらも離婚せずに関係を修復する場合、受けた精神的苦痛の度合いは、別居や離婚に至るケースに比べて小さいと判断される傾向があり、結果として慰謝料の額も低めになることが多いです。
慰謝料の金額額を左右する要素
浮気をした妻やその相手に対する慰謝料の金額を決定する際には、以下のような様々な要素が考慮されます。
- 婚姻期間の長さや別居期間
- 浮気発覚前の夫婦関係の状態(円満だったか、既に冷え切っていたか)
- 浮気の期間や頻度
- 浮気の悪質性の度合い(計画性、隠蔽工作の有無など)
- 浮気によって夫が受けた精神的苦痛の大きさ
- 当事者(夫、妻、浮気相手)の社会的地位や経済力
- 妻が浮気相手の子どもを妊娠・出産したかどうか
- 夫側に、妻が浮気に至ったことへの責任があるか など
これらの個別の事情に加え、夫や妻が提出する証拠や主張内容を踏まえて、最終的な慰謝料額がケースバイケースで決まります。
妻の浮気発覚後、離婚すべきか否かは慎重な判断を

妻に浮気をされたからといって、すぐに離婚を決断するのが最善とは限りません。離婚するかどうかの判断は、様々な側面から慎重に検討する必要があります。
慰謝料を得ても経済的にマイナスになる可能性
仮に慰謝料を獲得できたとしても、離婚に伴う財産分与の結果、経済的にはかえってマイナスになってしまうケースも少なくありません。
特に以下の3つの状況では、その可能性が高まるため注意が必要です。
妻が子どもの親権を得た場合
浮気をした妻であっても、子どもの監護状況などによっては親権者となることがあります。その場合、夫は妻に対して、子どもが成人する(場合によっては大学卒業まで)まで毎月養育費を支払う義務が生じます。子どもの年齢が低いほど、支払う養育費の総額は大きくなります。
夫に将来受け取る退職金が見込まれる場合
離婚時にまだ退職していなくても、将来夫が受け取る予定の退職金(婚姻期間に対応する部分)は、原則として財産分与の対象となります。勤続年数が長いほど退職金額は高額になる傾向があり、受け取る慰謝料よりも分与する退職金の方がはるかに大きくなる可能性があります。
夫の方が厚生年金を多く納付していた場合
婚姻期間中に納付された厚生年金(または共済年金)の保険料納付記録は、離婚時に夫婦で分割する「年金分割」の対象となります。たとえ夫の方が多く保険料を納めていたとしても、原則として婚姻期間中の部分は夫婦で均等に分割されるため、将来受け取る年金額で夫が損をする可能性があります。
離婚すべきか迷ったときの対処法
妻の浮気を受け、離婚すべきかどうかの判断に迷うときは、以下の3つのアプローチを試してみることをお勧めします。
自分の本当の気持ちと向き合う
まずは、ご自身の感情を整理することから始めましょう。妻への裏切りに対するショック、悲しみ、浮気相手への怒りなどで、冷静な判断が難しい状況かもしれません。
食事も喉を通らないほどの精神的ダメージを受けている方もいるでしょう。 慰謝料を求めるかどうかも含め、今後、妻との関係を修復したいのか、それとも離婚して新しい道を歩みたいのか。最終的な決断はご自身でするしかありません。様々な決断が必要になりますが、「自分がどうしたいのか」を最優先に考え、行動することを意識しましょう。
信頼できる人に相談する
一人で抱え込むのが精神的につらい場合は、ご家族や親しい友人に話を聞いてもらうのも良いでしょう。ただでさえ精神的な負担が大きい出来事に加え、離婚や今後の生活設計まで一人で考えなければならないのは、非常に厳しいものです。
ただし、離婚問題は非常にデリケートなため、他人に話しにくいと感じることもあるでしょう。そのような場合は、”良い意味で第三者”である弁護士に相談するのも有効な選択肢です。弁護士に胸の内を打ち明けるだけでも、気持ちが整理され、次に取るべき行動が見えてくるケースは少なくありません。
専門家のカウンセリングを利用する
もし妻が浮気の事実を反省しており、夫婦関係の修復にわずかでも可能性があると感じるなら、夫婦カウンセリングを受けてみるのも一つの方法です。これまで夫婦のあり方について深く話し合う機会がなかったかもしれません。
専門の心理カウンセラーに相談することで、お互いが抱える不安や誤解を解き、関係改善の糸口が見つかる可能性があります。また、第三者の客観的な視点からアドバイスをもらえることも、カウンセリングの利点です。
妻の浮気を理由に離婚する場合の4つのステップ

妻の浮気がどうしても許せず、離婚を決意した場合には、次の4つの点を意識して行動を進めてください。
- 浮気に至った背景・原因を探る
- 不貞行為(肉体関係)の証拠を確保する
- 住宅ローンなどの名義を確認・整理する
- 離婚後の生活設計を具体的に立てる
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1. 浮気に至った背景・原因を探る
離婚に向けた話し合いを円滑に進めるためには、なぜ妻が浮気に至ったのか、その背景や原因を冷静に把握しようと努めることが大切です。
考えられる原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 夫が仕事中心で家庭を顧みなかった、コミュニケーション不足
- 夫婦間の性生活に対する不満(セックスレスなど)
- 日常生活のマンネリ化、刺激を求めた
- もともと異性関係にルーズな傾向があった(結婚前からの浮気癖など)
- 浮気相手から強引に関係を迫られた
もちろん、浮気をした妻に非があることは事実です。しかし、一方的に怒りをぶつけるだけでは、お互いが感情的になり、建設的な話し合いができなくなる可能性があります。
もし、妻の浮気の原因の一端がご自身にもあると認められる場合(例えば、長期間の家庭内別居や、夫側の暴力・暴言など)、慰謝料の請求が認められなかったり、減額されたりする可能性もあります。したがって、具体的な手続きを進める前に、浮気の原因を客観的に探ることが重要です。
2. 不貞行為(肉体関係)の証拠を確保する
離婚を選択し、妻や浮気相手に対して慰謝料を請求するつもりであれば、不貞行為、つまり肉体関係があったことを示す客観的な証拠が不可欠です。
妻に浮気の事実を問い詰めてしまうと、警戒して証拠を隠蔽されたり、破棄されたりする危険があります。そのため、話し合いを切り出す前に、できる限り多くの証拠を集めておくことが極めて重要です。
不貞行為の証拠となり得るものには、以下のような様々なものがあります。
- ラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画
- 肉体関係を推認させるメール、LINE、SNSのメッセージ
- クレジットカードの利用明細(ラブホテル、浮気相手へのプレゼントなど)
- カーナビの履歴、GPSの記録
- 探偵事務所の調査報告書
- 浮気を認める内容の念書や録音
一見すると些細に見える証拠でも、他の証拠と組み合わせることで、慰謝料請求の交渉を有利に進める材料となる可能性があります。ご自身で「これは証拠にならないだろう」と判断して捨ててしまうのではなく、集めた証拠はできる限り手元に残しておき、法的に有効かどうかは弁護士に確認してもらうことを強くお勧めします。
3. 住宅ローンなどの名義を確認・整理する
持ち家や車など、夫婦共有の財産にローンが残っている場合、離婚後は原則としてローンの名義人(債務者)が支払いを続けることになります。
しかし、例えば住宅ローンの名義は夫だが、家の所有名義は夫婦共有になっている、あるいは妻になっている、といった「債務者と所有者の名義の不一致」があると、離婚後にローンの支払いを巡って深刻なトラブルに発展する可能性があります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、離婚時の財産分与などの手続きを通じて、ローンの債務者と財産の所有者の名義を一致させるか、あるいはその財産を売却して得た金銭を分配するといった方法を検討すべきです。金融機関との交渉が必要になる場合もありますので、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
4. 離婚後の生活設計を具体的に立てる
妻との離婚を決めたなら、離婚後のご自身の生活を具体的に計画することが不可欠です。
- どこに住むのか? (現在の住居、新しい住居の確保)
- 車はどうするのか? (所有権、ローンの有無)
- 子どもがいる場合、親権や養育、面会交流はどうするのか?
- 当面の生活費は確保できるか?
- 仕事への影響は?
新しい生活を始めるにあたって、何を決め、何を準備する必要があるのかを明確にしておくことが重要です。
もし、これらの生活設計の中で、離婚時に決めておくべき条件(例えば、現在の家に住み続ける権利、子どもの学費の負担割合など)があるのであれば、慰謝料請求や財産分与の話し合いと並行して、離婚の条件として明確に取り決めておく必要があります。
離婚を実現するための3つの方法

日本における離婚の方法は、大きく分けて3種類あります。多くの場合、【協議離婚】→【調停離婚】→【裁判離婚】の順に進められます。
1. 協議離婚
協議離婚とは、裁判所の手続きを経ずに、夫婦間の話し合いによって離婚の合意および離婚条件(財産分与、親権、養育費、慰謝料など)を決める方法です。
日本の離婚の約9割はこの協議離婚によるものです。お互いが離婚に合意し、諸条件について話し合いで決めることになります。離婚するかどうかは当事者の意思が最も尊重されるため、離婚条件についても、法律の範囲内であれば、基本的には当事者が合意した内容が有効となります。
例えば、法的な相場では慰謝料が100万円程度と見込まれるケースでも、妻側が早期の離婚成立を望み、「300万円支払う」と提案し、夫がそれに合意すれば、その金額で取り決めることも可能です。
ただし、慰謝料の額、親権の帰属、養育費の金額など、離婚条件について夫婦間の意見がまとまらない場合は、次のステップである裁判所を通じた手続き(離婚調停や離婚裁判)に進むことになります。
なお、話し合いで合意した内容は、必ず「離婚協議書」として書面に残しておくことが極めて重要です。口約束だけでは、後になって「そんな高額な慰謝料を払う約束はしていない」などと言い逃れをされる可能性があります。書面があれば、合意内容の確かな証拠となります。
さらに、将来的に相手が慰謝料や養育費の支払いを怠る可能性に備え、離婚協議書を「公正証書」として作成しておくことを強く推奨します。公正証書には、支払いが滞った場合に裁判手続きを経ずに強制執行(給与や財産の差し押さえ)が可能になるという強力な効力を持たせることができます。
2. 調停離婚
夫婦間の話し合い(協議)で離婚条件などがまとまらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることを検討します。
離婚調停とは、裁判官と民間から選ばれた調停委員(男女各1名が一般的)が夫婦の間に入り、中立的な立場で双方の意見を聞きながら、合意形成に向けて話し合いを進める手続きです。調停委員が解決案を提示したり、助言を与えたりして、円満な解決を目指します。
ただし、調停はあくまでも話し合いによる解決を目指す制度です。そのため、どちらか一方、あるいは双方が、どうしても譲れない条件を主張し続け、合意に至らない場合(調停不成立)、最終的な判断を裁判所に求める「離婚裁判(訴訟)」へと進むことになります。
なお、協議離婚の段階から弁護士に交渉を依頼することも可能ですが、調停離婚や裁判離婚においても、弁護士に代理人として手続きを依頼することができます。相手と直接顔を合わせたくない場合や、法的に不利な条件で合意してしまわないか不安な場合は、早い段階から弁護士に相談し、交渉や手続きを任せることをお勧めします。
3. 裁判離婚
離婚調停でも合意に至らなかった場合、最終手段として、地方裁判所に「離婚裁判(訴訟)」を提起することになります。
離婚裁判では、当事者双方が、法定の離婚原因(民法770条1項に定められた離婚が認められる理由。不貞行為はその一つ)が存在することや、慰謝料、財産分与、親権などの離婚条件について、それぞれの主張とそれを裏付ける証拠(浮気の証拠など)を提出します。裁判所は、これらの主張や証拠、その他の事情を総合的に審理し、離婚を認めるか否か、そして離婚条件(慰謝料額、財産分与の方法、親権者など)について法的な判断を下します。
調停や裁判によって離婚が認められた場合、たとえ相手(この場合は妻)が離婚に反対していても、法的に離婚が成立します。離婚を求めた側(この場合は夫)は、調停成立日または判決確定日から10日以内に、調停調書や判決書などの謄本を添付して、市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
この届出を怠ると、「過料」という行政上の制裁金が科される可能性がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。
離婚時に争点となりやすい2つの手続き

離婚の際には、慰謝料以外にも、主に【財産分与】と【親権】の2点について、夫婦間で意見が対立し、トラブルになる可能性が高いです。それぞれの交渉において、押さえておくべき点を理解しておくことが大切です。
1. 財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた共有財産を、離婚時に公平に分配する手続きです。財産分与の対象となる財産とならない財産があります。
財産分与の手続きの流れ
財産分与は、通常以下の手順で進められます。
・対象となる財産をすべてリストアップする(預貯金、不動産、車、保険解約返戻金、株式など)。
・それぞれの財産の価値を評価する(不動産や車は市場価格を調査)。
・分配の割合を決める(原則として2分の1ずつ。ただし、夫婦双方が納得すれば、異なる割合で合意することも可能)。
財産分与調停の申し立て 家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを進めます。
財産分与審判または離婚裁判での決定 裁判所が法的な判断を下します。
現金や預貯金のように分けやすい財産は金額で均等に分けるのが基本です。一方、不動産や車のように物理的に分割できない財産については、「財産を取得する側が、その市場価格の半分に相当する金銭を相手方に支払う」方法や、「財産を売却して得た現金を分配する」方法が一般的です。
財産分与の対象となる財産
原則として、結婚してから離婚する(または別居する)までの間に、夫婦が協力して得た財産が対象となります。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 現金、預貯金(夫婦どちらの名義でも)
- 不動産(土地、建物)
- 車
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 保険の解約返戻金
- 退職金(将来受け取るものも含む、婚姻期間対応部分)
- 家具・家電など(ただし、高価なものや美術品などを除き、日常生活で使用するものは価値が低いと見なされることが多い)
財産分与の対象とならない財産
以下の財産は、夫婦の協力とは無関係に得られた「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象にはなりません。
- 結婚前からそれぞれが所有していた財産(独身時代の預貯金、親から相続した不動産など)
- 結婚後であっても、相続や贈与によって一方の親族などから得た財産
- その他、個人の努力や才能によって得たと考えられる財産(例:個人的な趣味のコレクション、著作権など)
なお、借金(負債)については、原則として財産分与の対象にはなりません。個人の借金はその個人が返済するのが基本です。 ただし、夫婦の共同生活を維持するためにやむを得ず生じた借金については、「マイナスの財産」として考慮され、財産分与の際に清算の対象となる可能性があります。
【共同生活のための借金の例】
- 生活費の不足を補うためのキャッシングやカードローン
- 食費や日用品購入のためのクレジットカードの未払い分
- 家族で使用する車のローン
- 住宅ローン
- 子どもの学費や教育ローン
- 未払いの公共料金、家賃、医療費 など
2. 親権
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚後の子どもの親権者をどちらにするかを必ず決めなければなりません。日本では、離婚後の共同親権は認められておらず、父母のどちらか一方が単独で親権を持つことになります。
現状、日本では母親が親権者となるケースが多い傾向にあります。そのため、父親が親権を獲得するためには、親権者として適格であることを示すためのポイントをしっかり理解し、準備を進める必要があります。
親権者を決める際の6つの判断基準
家庭裁判所などが親権者を判断する際には、どちらの親が親権者となることが「子の福祉(子どもの幸せや利益)」に最も適うか、という観点から、以下の要素を総合的に考慮します。
- 監護に対する意欲と愛情(子ども本位の姿勢) 親自身の都合ではなく、子どもの健全な成長を最優先に考え、行動しているかが最も重要視されます。具体的には、子どもとの時間を確保する努力、日々の世話、健康管理への配慮、教育への関与などが評価されます。
- 子どもの意思 子どもがある程度の年齢(一般的に10歳以上、15歳以上では特に重視)に達しており、自分の意思を表明できる場合には、子ども自身がどちらの親と暮らしたいと考えているかが尊重されます。
- 監護能力(心身の健康、経済力、居住環境) 子どもを健全に育てていくための親自身の心身の健康状態、安定した経済力、子どもに適した居住環境が整っているかが評価されます。例えば、一方の親に虐待の事実があったり、深刻な浪費癖があったり、精神疾患により養育が困難な状況にある場合は、他方の親に有利に働く可能性があります。
- これまでの監護実績(主たる監護者) これまで主にどちらの親が子どもの日常的な世話(食事、入浴、寝かしつけ、送迎、学校行事への参加など)を担ってきたかという実績が重視されます。幼稚園や保育園の先生、学校の教師などからの証言(陳述書など)が有効な場合があります。
- 環境の継続性(現状維持の原則) 親の離婚によって、子どもの生活環境(住居、学校、交友関係など)が大きく変わることは、子どもにとって負担が大きいと考えられています。そのため、可能な限り、これまでの生活環境を維持できる親が有利になる傾向があります。頻繁な転勤や出張が多い親は、この点で不利になる可能性があります。
- 面会交流への許容性・協力的な姿勢 親権者にならなかった方の親と子どもが、離婚後も定期的に交流を持つこと(面会交流)は、子どもの健全な成長にとって重要であると考えられています。そのため、親権を希望する親が、他方の親との面会交流に対して協力的で寛容な姿勢を示しているかどうかも判断材料となります。「相手には絶対に子どもを会わせたくない」といった排他的な態度は、子どもの福祉を考えていないと見なされ、不利になる可能性があります。
父親が親権を獲得するためのポイント
母親が有利とされる傾向の中で、父親が親権を獲得するためには、特に以下の点を具体的に示していくことが重要です。
- 母親よりも安定した経済基盤があり、子どもにより良い生活環境を提供できること
- 子どもと過ごす時間を十分に確保できる労働環境や生活スタイルであること(柔軟な勤務時間、在宅勤務の可否、残業の少なさなど)
- 祖父母など、育児をサポートしてくれる協力者(監護補助者)がいること
また、母親側に、子どもの養育環境として不適切な事情(ネグレクト、精神的な不安定さ、子どもへの悪影響がある異性関係など)があれば、それらの事実を客観的な証拠とともに主張することも必要になる場合があります。
親権が獲得できなかった場合
もし親権を獲得できなかったとしても、子どもとの関わりを維持することは可能です。そのための重要な権利が「面会交流」です。 離婚時に、面会交流の頻度(月〇回、長期休暇中など)、時間、場所、方法などを具体的に取り決めておくことで、親権者とならなかった親も、子どもと定期的に会い、コミュニケーションをとる機会を得ることができます。面会交流の条件は、離婚協議書や調停調書、判決などで明確に定めておくことが重要です。
また、理論上は、財産管理権を含む「親権」と、子どもの世話や教育を行う「監護権」を分離し、父親が監護権者となることも考えられますが、これはあまり一般的な方法ではなく、母親の同意が得られない限り、裁判所も認めることは稀です。
妻の浮気に関する慰謝料判例紹介

妻の浮気に対する慰謝料の目安は50万円から300万円程度と述べましたが、実際の金額は、離婚の有無、浮気の態様、証拠の質、当事者の反省度など、多くの要因を総合的に考慮して個別に判断されます。
参考として、過去の裁判で認められた慰謝料額の事例をいくつかご紹介します。
事例1:不貞行為が原因で離婚に至ったとして、浮気相手に慰謝料請求
夫が、妻とその浮気相手の不貞関係が原因で離婚に至り精神的苦痛を受けたとして、浮気相手に慰謝料を請求した。
裁判所の判断
妻の浮気発覚後、夫婦は別居し、その後協議離婚。離婚に際し、夫は自宅土地建物の妻の持ち分をローン完済後に無償で取得する合意をしており、これにより妻に対する慰謝料請求権は実質的に放棄(免除)されたものとみなされた上で、浮気相手に対する慰謝料額が判断された。
認容額: 200万円
事例2:不貞行為により夫婦関係が悪化したとして、浮気相手に慰謝料請求
夫が、妻とその浮気相手の不貞関係によって夫婦関係が悪化し精神的苦痛を受けたとして、浮気相手に慰謝料を請求した。
裁判所の判断
不貞行為が少なくとも約2年9ヶ月にわたり継続していたことを認定。一方で、浮気関係が始まる前から夫婦関係が相当程度悪化していたこと、子どもの年齢が比較的高い(当時21歳・18歳)ことなどが考慮された。
認容額: 100万円
事例3:不貞行為により夫婦関係が破綻したとして、浮気相手に慰謝料請求
概夫が、妻とその浮気相手の不貞関係によって夫婦関係が破綻し精神的苦痛を受けたとして、浮気相手に慰謝料を請求した。
裁判所の判断: 浮気発覚まで夫婦関係が円満であったこと、夫婦間に子どもがいること、浮気によって夫婦関係が破綻に至ったことを認定。
一方で、浮気相手が「夫婦関係は既に破綻している」と信じていたこと、交際期間が比較的短い(4ヶ月)ことなども考慮された。 認容額: 150万円
事例4:妻と浮気相手に対し、連帯して慰謝料支払いを請求
夫が、妻とその浮気相手の共同の不貞行為により婚姻共同生活の平和を維持する権利・利益を侵害され精神的苦痛を受けたとして、妻と浮気相手の両方に対し、連帯して(どちらか一方が全額支払えば他方の支払い義務も消滅する形で)慰謝料の支払いを求めた。
裁判所の判断
妻と浮気相手との間のLINEのやり取りなどから、不貞関係の存在が強く推認されると判断された。
認容額: 135万円(妻と浮気相手の連帯支払い)
事例5:不貞行為により夫婦関係が破綻したとして、妻に慰謝料請求
夫が、妻が浮気相手と不貞行為を行ったと主張し、妻本人に対して慰謝料の支払いを求めた。
認容額: 165万円(弁護士費用15万円を含む)
これらの判例からも分かるように、慰謝料額は個別の事情によって大きく変動します。
まとめ

妻の浮気が発覚した場合、離婚するかどうかにかかわらず、妻とその浮気相手に対して慰謝料を請求する権利があります。慰謝料の目安は一般的に50万円から300万円程度ですが、不貞行為(肉体関係)の証拠の有無や質が、認められる金額に大きく影響します。
また、離婚を選択する場合、慰謝料だけでなく、財産分与、年金分割、そして子どもがいる場合は親権や養育費など、決めなければならない事項が数多く存在します。これらの手続きは複雑で、感情的な対立も生じやすいため、多大な時間と労力を要します。
ご自身にとって最善の解決を図り、法的に不利な状況に陥らないためにも、浮気問題への対応は、早期の段階から法律の専門家である弁護士に相談し、サポートを求めることを強くお勧めします。
弁護士は、個別の状況に応じた最適な対応策をアドバイスし、証拠収集の助言、相手方との交渉代行、調停や裁判になった場合の代理人活動など、あらゆる段階であなたを力強くサポートします。一人で悩み、精神的に追い詰められてしまう前に、まずは一度、信頼できる弁護士にご相談ください。